緊張感の根底にあるものは?
あがり症の対策としては、まずは、適切な情報量や構成で内容を準備すること。

古垣講師
こうして話す際の頭の負荷を軽減すると、緊張時の焦りや不安に対応できる、意識の余裕が生まれます。
もう一つ点検したいのが、考え方や感じ方のクセです。
例えば、日常の中で、以下のような思いを持つことはあるでしょうか。
| 【感じ方や考え方のクセ】 |
|---|
| ・何かと心配し過ぎてしまう ・他人を尊敬しすぎることがある ・つい優劣を感じてしまう ・他人の言動が気になる |
全部ではなくても、いくつかは当てはまるかもしれません。
これらの思いは、「他者の言動」や「周囲の出来事」で、心が揺れ動きやすいタイプによく見られます。

古垣講師
これを「他人軸」と呼びます。
他人軸への傾倒が強い場合、以下の状況で緊張が激しくなることがあります。
- ・自分を評価する人が目の前にいる
(他人軸の人にとっては、より影響を受けやすい状況) - ・周囲の人の競争意識が強い
(ただし、自分の方が優れているとわかると、落ち着く)

古垣講師
他人のチカラにより、自分の評価が左右されそうな場面です。
なぜ他人軸になるのか
他人軸になるのは、生育環境において、「ありのままの自分」ではいられなかったことが大きな要因だと考えられます。
- ・背伸びして「大人のように行動しなくてはいけない」環境
- ・過保護で自分の自我が育たなかった環境
こうした環境が、影響している可能性があります。
ただし、あなたは他人軸のおかげで、周囲に向けて何かと配慮ができる人かもしれません。
だから、発表などの事前準備では、他人軸を共感力として使えば、人に寄り添ったアイデアを生み出すのに、役立つこともあります。
しかし、「準備した内容を発表する瞬間」になっても、他人軸の在り方を変えられずに周りのことがどうしても気になる。
すると、他人の反応が気になり、緊張感が高まってしまうことがあります。

古垣講師
意識における「他人軸への偏り」を変えない限り、強い緊張感を変えづらいことがあります。
他人軸と自分軸を行き来する
他人軸の対極になるのは「自分軸」です。
- ・自分の失敗を、真摯に、でも温かく受け止めることができる。
- ・困難な環境においても、物事に取り組む方法やモチベーションを自分で作れる。
- ・他人を責めるのではなく、自分にできることを考えようとする。
- ・自分を認め、自分自身で安心感を作れること
- ・困難があっても、周囲を批判せずに、柔軟に対策を考えられること
- ・優劣をつけずに、フラットに人と関わる意識をもつこと
そうしたものが自分軸の心のあり方です。
そして、普段の行動の中で、自分軸を育てていくことができます。
| 自分軸を育てる、行動の例 |
|---|
| 仕事のミスを受け止めながら、「自分なりに努力できたこと」も認めて自分で適切に評価する。 |
| 誰かの意見に完全に頼るのではなく、自分なりにじっくりとやるべき方針を考える。 |
| 仕事やプライベートで悩みがあるとき、「相手が悪い」などと他人を批判するだけでなく、自分にもできることを考える。 |
また、完全に他人軸を消し去るのではなく、心のどこかに維持しておくほうが現実に対応しやすいと考えられます。
自分軸だけに基づいて、「人の気持ちに配慮しない振る舞い」になると、周囲と人間関係を築くのが困難になるためです。

古垣講師
「他人軸」と「自分軸」を必要に応じて行き来できると、適応できることの範囲が広がります。
自分軸で行動するときの注意点
「自分軸に基づいて行動する」とは、悩みを抱え込むことではありません。
悩みを抱え込むことの奥には、自分の未熟さを感じるゆえに、「私はがんばらないといけない、努力しないといけない」そんな思いが隠れていることがあります。
それは、自分の欠落感からくるものであり、他者と並ぶために努力をするという、結局は他人軸であることが見え隠れしています。
邪魔なプライドは消して、他人に教えてもらったり、協力してもらったりすること。
そうした対策に専念することこそが、成熟した「自分軸」の在り方です。
また、自分軸とは、自分の考えのみを信じて「傲慢」になることとも違います。
傲慢になるのは、他人との比較で自分を「上」と感じ、安心したい気持ちがあるからです。

古垣講師
「他人より上 or 下」という感覚ではなく、フラットに人と関わる意識を持つことが、健全な自分軸を保つためには必要です。
まとめ
これが実践的な「自分軸」であり、あがり症と根本から向き合うために役立ちます。日常のさまざまなことの自信にも繋がるでしょう。

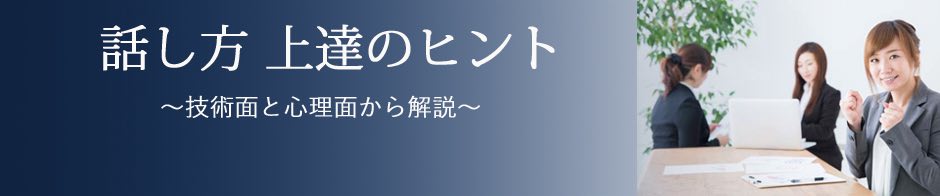


 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康