| こんなお悩みはありますか? |
|---|
| ・普段から、深く考えずに話している気がする |
| ・直感的な言動が多く、周囲を説得するのが難しいことがある |
| ・危機を感じやすく、緊張感が生じやすい |
深く考えずに話すとは、自分の話を「様々な角度から点検しづらい」ということ。
その場合に、「ディスカッション」で発言したり、説得力のある話をすべき場面でも、十分な検討ができないまま、話をしてしまうことがあります。
さらに、理性的な感情のコントロールが難しく、人前で話すときに危機感が大きくなり、緊張しやすくなることもあり得ます。

古垣講師
これらは、「理性的に思考するコツ」が分からず、直感に任せるような言動が増えている状況です。
こうした、理性と直感の関係性を、心理学の世界では「速い思考」「遅い思考」と呼ぶことがあります。
以降で詳しくご紹介します。
「速い思考」と「遅い思考」
心理学を学んでいる人には、わりと知られているのが、人の持つ「速い思考」と「遅い思考」という2つの側面です。
もともとは、2000年に心理学者のKeith StanovichとRichard Westが二重過程理論を発表。
さらに、ノーベル経済学賞を受賞したDaniel Kahneman(心理学者、行動経済学者)が著書、ファスト&スロー(つまり、速い思考&遅い思考)として広めました。
速い思考と遅い思考を比較すると、以下のようになります。
| 速い思考(システム1) | 遅い思考(システム2) |
|---|---|
| 直感的 | 熟考的 |
| 速い | 遅い |
| 進化的には古いシステム | 進化的には新しいシステム |
| 無意識的 | 意識的 |
| 自動的 | 制御的 |
参考:Dual-process theories of higher cognition(Evans & Stanovich, 2013)
「速い思考」とは結局なんのこと?

速い思考とは「直感を生かして、深く考えない思考」です。
様々な点検するべきことがあっても、考えることを早めに切り上げて行動に移します。
こうした「速い思考」は、太古の世界のように猛獣と出会う状況なら、とても役に立ちます。
猛獣は人に合わせて待ってくれるとは限りません。
だから、人も迅速に判断をくだすほうが、生き残る確率が高まります。
しかし、直感的な思考の弱点は、理性的な思考力を失いがちなこと。
例えば、仕事上の役割が高度になり、理性的な話し方が必要になる場合は、速い思考のままでは対応が難しいことがあります。
その場合に、次にご紹介する「遅い思考」を身につけることが、お悩みの突破口となることがあります。
遅い思考とは? どう役立つか?

多角的な検討や、数段階の点検を踏まえた思考ができることが、遅い思考です。
頭の中の状態としては、一つの情報に捉われずに、複数の情報を保持しながら、思考を進める状態になります。
例えば、一つの意見を受け入れるだけでなく、自分の頭で「本当にそうだろうか?」と、他の案と比較検討をしてみる。
正確には「遅い思考」というより、「じっくり考える思考」という方が良いかもしれません。
直感的な「速い思考」に比べると、脳に負荷が掛かります。
しかし、考えるのが大変でも、他人に判断を委ねずに、自分自身で適切な方針や意見を考える。
この力が、社会で生きていくために必要になるタイミングが来ることがあります。

古垣講師
どうトレーニングすれば、じっくり考えることができるのか。次の項目で「仮説思考」を紹介します。
どうトレーニングすれば良いのか
仮説思考から始める
一つの考えに捉われないように、「他人から聞いた意見」や「自分のアイデア」を「仮説」として扱うことが、一つの道です。
「いいな!」と思う意見があっても、それを一つの仮説や足場にして、他のアイデアや検討の余地を考える。
こうした習慣があると、多角的に考えて話すことが身についていきます。

古垣講師
ただし、仮説思考は「なんでも仮説に留めれば十分」とは言えないのです。
注意したいのは、仮説を検証する力があるかどうか。
道に迷いやすい人は、目の前に目的地があっても、よく検証できずに他を探して道に迷うことがあります。
同様に、検証する力がないと、多角的に考えるだけで、最善の選択肢を見逃してしまうことがあるのです。
そこで必要になるのが、解像度を高める(細やかに考える)ことや、「論理的思考」「批評的思考」と呼ばれる深く点検する力です。
当会でも、こうした思考法を元に、会議などの話し方を磨く講座があります。
緊張する状況でも理性的に事態と向き合う
焦りやすい状況でも神経を高ぶらせず、理性的に事態と向き合うこと。
自分の焦りに対して適切な調整を試すことで、速い思考から脱することが可能になります。
認知行動療法などで合理的な考え方、捉え方を身に着けていくことも、その一つだと言えるかもしれません。

「考えて話せない」「人前で緊張する」などの「話す悩み」に対する適切な学び方を、論理的に解説。当会の推奨講座も掲載した一冊です。当会のメール配信(無料)に登録後、ダウンロードできます。
ダニエル・カーネマン(2012)ファスト&スロー(上).村上章子(訳)早川書房:東京.
Evans, J. St. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. Perspectives on Psychological Sciences, 8, 223-241.
Stanovich, K. E., & West, R. F. (1998). Individual differences in rational thought. Journal of Experimental Psychology: General, 127, 161-188.

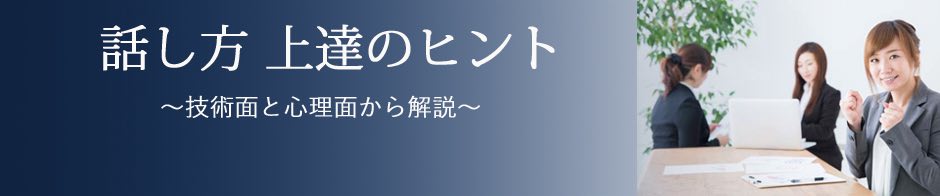

 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康


