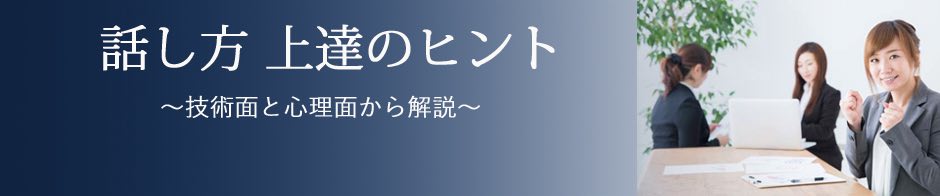教室は「恥をかいて良い場所」なので、ハードルを上げずに参加して頂けたらと願っています。
ただ、「レッスンに付いていけるか不安」「どう学んだら上達するのか」など不安をお感じになる方もいます。
そこで参考までに、いくつか学びのポイントをご紹介します。
ビギナー向け:ハードルを上げずに参加する

話のニガテ感のある人の中には、「自信がなく、他人からの評価のされ方が気になる」人がいらっしゃいます。
だから、受講するときに「他者にどう感じられるか」が気になり、不安になったり、緊張されたりする人もいます。
だけど、意外とお悩みの人は多く、決して「珍しいお悩み」ではないのです。
その練習のために通うのですから、自分のありのままの姿を見られても、非難される場所ではありません。
また、他人と同じではなく、自分なりのゴールを見つけることも大事です。
「普通に話せるようになりたい」
「他人と同じように話せるようになりたい」
これらは、他人との比較の上で設定されたもので、より恥をかくことを恐れます。
そのため、自分に必要な点が、細やかに見えづらくなることがあります。
自分のありのままの姿を見つめると、何が必要で、自分が学びたいことか、視界がハッキリとしてくるものです。
もし、
「自分を客観視したい」
「話し方の問題がどの程度なのか、現在地を知りたい」
こうしたご希望があれば、最初はトレーニングではなく、カウンセリングから受講されても良いでしょう。
当会では、心理チェックツールを用いて、お悩みの原因分析と適切なコース選択、その人に合ったコースカスタマイズもご紹介しています。
話し方・あがり症総合カウンセリング
話すことの魅力を楽しむ
例えば説明なら、「自分ならもっと分かりやすく説明できる」という欲が出たら、話す不安はかなり軽減できます。
話すための技法が身に付いてくると、「うまく話せたらいいな」という思いから、だんだんと「人を楽しませたい」「役に立ちたい」という思いに変わっていくのですね。

講師である私自身も、もともとは話し方で悩んでいた人間です。
ただ、私はたまたまテレビ業界に居て、伝え方を指導してくれる先輩方に出会いました。
身につけるまでは非常に苦労しましたが、一度コツが分かると、むしろ自分の頼れるスキルになったのです。
もともと話せなかったから勘に頼らずに、技術をしっかり身につけることができたのですね。
また、自分が悩んできた分だけ、コツをどう使えばよいか、人に教えることもできました。
その経験が、話し方講師の仕事にも役立っています。
話せるようになると、どう変わるか

これまで、3,000人以上の皆様にのサポートをしてきましたが、話せるようになると、社会に参加しやすくなる面があると私は感じます。
受講される皆様からも、
「話に自信を持てて、積極的に仕事に関われる」
「立場を背負って話す際に、その役割を楽しめる感覚がある」
そうしたお話をお聞きすることが多いです。
また、話すという行為は、その人が「どのような考えや気持ちを持っているか」を周囲に知らせ、安心感を与える効果もあります。
だから、組織やお客様、協働する皆様とより深く繋がる力にもなります。
どう学ぶか:練習で成功するより大事なこと

講座は「恥をかいてよい場所」なので、緊張していても現時点の力を試すつもりで挑んでみましょう。
なお、教室で話を成功させる以上に大切なのは、「自分の出来ていない点」を見つめることです。
これは「ネガティブになる」ということとは、別物なのです。
例えば、学校で成績を上げるなら、テストで成果を試して、自分のできない点に注目します。
英単語を理解していなかったとか、数学の公式を覚えていなかったとか。
そうやって、自分の苦手なポイントを復習することで、成績が上がりやすくなるわけです。
話し方も、何が苦手だったのか、実習をやる中で新たな発見があります。
「緊張するが、話の内容は問題ないと思っていた」場合でも、実際に学んでみると、意外と内容面の自信が乏しかったことに気づいたり、これから何に注力すると良いかが分かったりします。
精細に見つめることを「解像度を高める」と言いますが、まさにレッスンにおける発表は、強化すべきポイントを細やかに分析できる機会なのです。
執筆者
 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康
【プロフィール】株式会社ワクリ代表。NHK(総合、Eテレ)の番組制作や番組サイト編集に携わりながら、話し方団体で講師を務める。現在は話し方講師、スピーチライター、認知行動療法&産業カウンセラー。
講師詳細 話し方オンラインレッスン開催