| こんなお悩みはありますか? |
|---|
| ・自分の余裕の無さを感じる場面がある |
| ・昔から緊張しやすい |
| ・昔から即興で話すことがニガテ |
緊張や即興のニガテ感には、実は思考や感情のキャパシティの問題が関わることがあります。
この記事で、その原因と対策を詳しく解説しています。
頭が一杯で、余裕の無さを感じますか?
例えば、日常でこんな気持ちになることはあるでしょうか。
「学びや仕事の難易度が高いと、頭が一杯になり、先に進みづらい」
「作業が面倒なときは、途中から考えて理解することが難しくなる」
こうした状態は、まさに「脳への負荷が高い」状態です。
認知心理学の言葉を用いると、「認知的負荷が高い状態」と言えます。

古垣講師
負荷と言えば、通常は重いものを持つなど、体に負担が掛かること。一方で認知的負荷は、脳で思考する際の負担のことです。
そもそも脳が一時的に処理できる量は有限であり、人それぞれに容量が違っています。
そのため、人によっては、認知的負荷(脳への負荷)の高い作業をする際に、作業容量が一杯になり、それ以上は作業しづらいような、ストレスを感じることがあるのです。
だからと言って、難しいことを考えられない訳ではありません。
ただ、自分がまだ理解できていないこと、習熟できていないことは脳にとって慣れない作業のために認知的負荷が特に高く、頭がより一杯になる感覚を覚えることが多いようです。
認知的負荷の話し方への影響を点検する
個人差はありますが、例えば以下のような実感を抱く方が多いです。
即興で話すより、準備したほうが要領良く話せる
「即興の話」は、一度に処理する手間が多い状況です。

古垣講師
即興では、一度に整理したり、組み立てたり、脳の作業がたくさん発生します。
一方で「準備すれば話せる」というのは、短時間で一度に情報を処理するのではなく、時間をかけて脳の一時的な負荷を分散しながら話を構築できるので、比較的、ラクな作業です。
そのため、準備時間がある方が「脳の余力」が生まれやすく、自信が湧く人もいます。
緊張下で、冷静さを欠いた行動が増える
緊張すると、認知的な余裕がなくなり、冷静に考えることが難しくなります。この性質が過剰な人は、普段しないようなミスを、緊張下ではよく起こしてしまうことがあります。
軽度な人だと、ミスとまでは言わないまでも、思考の効率の低下や、視野狭窄的な見方(思い込み)が増えていることがあります。

古垣講師
緊張すると、浮足立ったような感覚を覚えるのが、まさにこれです。
説明する際などに、言葉が足りないことがある
「適切な表現が出てきづらい」のも、頭が一杯になりやすい人にしばしば起きることです。ただし、言葉をうまく使えるかどうかは、普段からの習慣も関わると考えられます。
また、「相手にとって理解しやすい伝え方」を想像する余裕が無い事例も、しばしば見受けられます。

古垣講師
その他、事態を俯瞰することや、客観的に考察するといった意識の余裕がないこともあります。
認知的負荷に向き合うための対策
以下のポイントに沿って、「認知的負荷が高いときでも、うまく情報を構築するコツ」を学ぶことがお勧めです。
効率の良い認知処理の方法
情報の要不要の判断がうまくできない人が多いので、まずはその方法をしっかり学ぶことが推奨です。例えば、話の焦点はなにか、焦点ではないものはなにか。そうした判断の方法(情報整理)を、当会のトレーニングでも詳しくご紹介しています。

古垣講師
当会では、情報構築のためのコツを学んで頂いています。
そもそもの認知的負荷を減らす
緊張感などは、その人自身の考え方や感じ方のクセが、余計に拍車をかけていることがあります。認知行動療法では、そうした自分への負荷を合理的に改善していくことができます。
認知的体力を養う
たくさんの情報が押し寄せた際に認知処理が十分にできず、中途半端な伝え方や、パフォーマンスの乱れに繋がっている人は、少なくないです。
当会のレッスンでも、多くの情報を処理されようとすると、パフォーマンスが極端に低下する方がしばしばいらっしゃいます。
ですが、練習を積む中で、だんだんと多くの情報に接しながらも落ち着いて考えることができるようになっていきます。
つまり、適切な練習を通して「認知的体力を養う」ことも、お勧めのポイントです。
認知的負荷に慣れることはできるのか?
実際に認知的負荷に慣れる練習をされた皆様の声をご紹介します。
「話すときの混乱の原因が分かる」(50代 料理教室講師)
話す内容の整理や、情報量について考える必要があることが分かりました。「話下手」というより、「内容の多さ」が混乱の原因になっていた気がします。いままで単に「話すことが苦手」という感覚でしたが、具体的な対策が見えてきました。
「練習量より大事な、話すための下地」(40代 会社経営者)受講の目的は上がり症を改善したいということでした。躓くポイントがあるたびにワーキングメモリーのお話をしていただいたおかげで、話の組み立て方を工夫するだけでつっかかりが減ることを経験できました。
講義の通りに文章を作った後、少し時間をおいてみたり、自分にメールを送って見たりして、客観的に見てみる方法を試して、試行錯誤を繰り返して、より洗練された文章をつくることが出来ることを学ぶことが出来ました。
練習量ももちろん大切ですが、自分にとっても聞き手に取っても分かりやすい文章にすることで、スムーズなスピーチになるということが一番大きな収穫だと思います。
この度はありがとうございました。
リンク:「個別レッスン」の体験談一覧へ

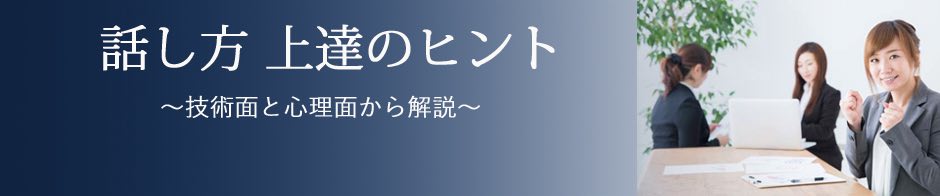


 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康

