ここでは、そもそも「スピーチに求められること」を踏まえ、必要な構成法をご紹介します。
スピーチに求められることと構成の関連性
例えば、「事実」だけを伝えるなら、聞き手には「報告」に聞こえます。
一方で「スピーチ」は、「事実」+「メッセージ」の伝え方がお勧め。
| 伝え方の違い | |
|---|---|
| 事実のみ | 〇〇はこんな本でした。(事実) |
| 事実+メッセージ | 〇〇はこんな本でした。(事実) 仕事の発想を広げるのに役立つと感じます。(メッセージ) |

古垣講師
「メッセージ」とは、自分の経験を通して伝えたいこと。つまり、「意見」「アイデア」「所感(感想)」などです。
聴衆は大切な時間を割いて、個人のスピーチを聞いています。
それは、「その個人だから語れること(メッセージ)」をどこかに期待する心理が、芽生えやすい状況とも言えます。
そのためスピーチの構成法も、「事実」を踏まえながら「メッセージ」を伝えるという構成を練習しておくのがお勧めです。
3部構成をマスターしよう
事実を踏まえたメッセージの伝達を、シンプルに実現するのが3部構成です。
| 3部構成 |
|---|
| 1.序論・・・話の導入、あるいはメッセージ紹介 |
| 2.本論・・・具体例と結論への流れ |
| 3.結論・・メッセージ紹介 |
本論で「事実」を踏まえておき、結論で「メッセージ」を伝えること。
実際のスピーチなら以下のようになります。
| 3部構成のスピーチ |
|---|
| 1.序論「先月、伊豆を旅行して感じたことをお話しします。」 |
| 2.本論「もともと、ネットで調べたうえで、温泉や美味しいものを楽しもうと、一泊二日の旅をしてきました。どれも良かったのですが、たまたま旅の途中で、珍しい地ビールを飲んだのです。これがウマイ、とても珍しい味でした。〜具体例が続く〜」 |
| 3.結論「ネットの検索では見つからない、思わぬ出会いが旅にある。そんな話をしました」 |
このように、具体例を使ってメッセージを印象付けるのが、スピーチの基本的な構成法です。
当然ですが、話す前に結論となる「メッセージ」を絞っておくことが大事になります。
そのため、ネタの見当がついたら、「結論」から考えること。
次に「本論」を整理して、「序論」を考えます。以下は、その順序に沿って、ポイントをご紹介します。
本論のつくり方
本論では、結論を裏付ける流れを作ります。
扱うネタは、データなどの情報も良いのですが、「自分の体験」をまずは語れるようになるのがお勧め。
その中でもスピーチに使いやすいのは、苦楽の変化が味わえる話です。
「苦労した結果、よいことが起きた」、あるいは「楽しい気分にうつつを抜かしていたら、思わぬ苦しみを味わった」など。
あらすじだけでなく、「感情の変化」や「場面」を丁寧に語れば、臨場感も出るし、2~3分間のスピーチを作りやすくなります。
そのためにチェックしたい点が、「事柄」と「感情」を、どちらも盛り込んであるか。
「事柄(その場で起きたこと)」は、自分が見た光景や聞いたセリフ、人の体がどのように動いたかなど。
「感情」は、そのときに味わった喜怒哀楽や期待感、恐怖感など。
事柄だけを描くと、味気ない話になりがちです。
感情だけだと、なぜそのような感じ方をするに至ったかが、聞き手には分かりません。

古垣講師
事柄と感情の両方を語ると、相乗効果でしっかりと内容が伝わります。
序論のつくり方
「結論から先に話す」とよく言われます。
とくに会議など、端的に話の意図を知らせる場なら、結論を先に出すことが有効です。
ただし、3分間スピーチのように長い話では、最初に結論を出すと、ネタバレ感や予定調和感が出てしまうことがあります。
結論となるメッセージは、話の内容によっては隠すこともアリです。
ただし、少なくとも、話の全体像を序論で示しておくことは必要です。
「先月、伊豆を旅行したときのについての話です」など、何の話か「おおよそのことが分かる言葉」を入れましょう。
「朝起きて、駅に向かったのですが・・・」など、いきなり本論となる具体例から語り始めると、聞き手は何について語るのかを理解できないまま、スピーチに付き合わないといけません。

古垣講師
全体像が不明なまま話が続くと、聞き手が疲れやすくなります。
よほど話し慣れている場合は、具体的な情景から話を始めることもあります。
起承転結のデメリット
長らく情報の伝え方を研究してきましたが、残念ながら多いのが、無理に「起承転結」の型にはめようとする人です。
起承転結はそもそも漢詩をつくるための構成法であり、事実に基づいたスピーチでは「転(=変化)」をつくることが困難なことがあります。
起承転結にしようとして、唐突な話を「転」としてスピーチの途中に入れる人もいます。
その場合は、聞く人の理解が追いつきづらいスピーチになるため、注意が必要です。

古垣講師
「起承転結を使っても、破綻のない話」なら良いのですが、「無理に使う必要性はない」と私の教室ではお伝えしています。

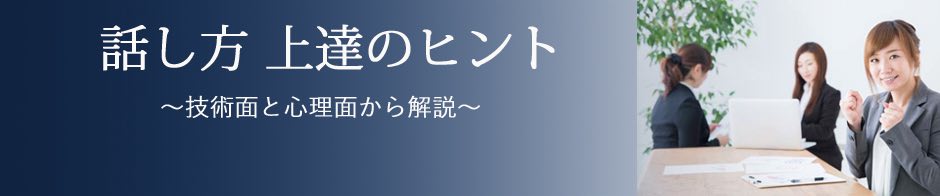


 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康


