| こんな実感はありますか? |
|---|
・話をしている最中に、混乱することがある(迷子になる) ・説明を分かりやすい道筋で話すのが苦手 ・聞く人が、整理しながら理解している印象がある |
当会では、3,000人以上の皆様とレッスンを開催してきました。
その中で明らかになってきた傾向ですが、説明が苦手な人は、以下のパターンが習慣になっていることがあります。
伝えたいことを、頭の中で言葉として浮かべる |
「。」で区切る一文に、無意識に様々な情報を詰め込んでしまう。
一方で説明を上手に語る人は、以下の作業を行います。
伝えたいことを、頭の中で言葉として浮かべる |
「様々な一文のパーツ」とは、「ポイント」「前置き」「具体例」など、役割を与えた文をいくつか作成すること。
上手な人は、「。」で区切るまでに、多くの役割を持たせません。
以下の例は、一文に一つの役割を与えた伝え方です。
| 一文に役割を与えた例 |
|---|
この企画は、〇〇というコンセプトがあります。(ポイント) |
一見、「型にはめるようで、面倒」「自分の説明に当てはめて、うまくいくのだろうか」と感じる方もいらっしゃいます。
しかし、文の様々な役割を理解して、頭の中に型ができれば、それほど考えずとも自然と機能的な文を作成して、組み合わせていけます。
また、もう一つ重要なことが、無駄を見つけやすくなることです。文に役割を与えると、情報の要、不要が選別しやすくなります。
よくご相談頂くのが、「上手な人は無駄の少ない言葉で、的確に話す。自分にはそれができない」というものです。
専門的には「捨象」と呼ばれますが、無駄な情報を「捨」てることで、残った要素が「象(カタチ)」になる。
そのためには、情報の役割を理解して、無駄のないパーツで話の模型を組み上げていくこと。
私が元々所属した放送の世界でも、「話は構築物」と考えられることがありました。
ぜひ、説明上手になるため、文に役割を与えて組み上げることに挑まれてください。

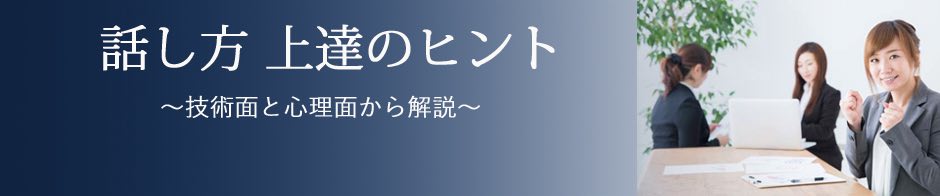





 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康