| こんな悩みはありますか? |
|---|
| 発表の前は、練習を長々と続けてしまう |
| 練習しないで本番に挑むと緊張が激しい |
| 話の適切な練習量が分からない |
スピーチやプレゼンテーション、説明などは、話す前にどれくらいの練習が適切なのか。

古垣講師
実は、練習量によっては、かえって良いパフォーマンスに繋がらないことがあるのです。
過去3,000人以上の話し方トレーニングと、認知行動療法によるサポートの経験をもとに、理想的な練習の仕方について解説します。
練習と緊張感の関係性は?
練習のやりすぎが良くない理由
「本番での失敗が怖くて、とことんまで練習してしまう」
緊張しやすい皆様から、そうした声をよくお聞きします。
例えば、「不安から、本番さながらの練習を何度もする」「不安で、一言一句を覚えようとする」など、完璧さを求めるように練習を頑張ってしまう。

古垣講師
自分の中に安心感が湧かないと、完璧さを求めて練習を続けてしまいます。
不安からとことん練習をすることは、認知行動療法の中では「安全確保行動(安全行動)」と呼ばれます。
失敗しないように、「安全を確保するための行動」を行うのですが、不安が軽減されることはありません。
こうして、練習はするけども、緊張感が維持されてしまうことがあります。
しかも、「練習のやり過ぎ」は交感神経の高ぶりが鎮まらず、かえって「硬くて、ぎこちないパフォーマンス」に繋がることがあるのです。
(話を噛みやすくなる、勢いが余って早口になるなど)
適切な練習は本番の良いパフォーマンスに繋がりますが、「失敗を恐れて練習をやり続ける状態」に陥ると、緊張感を固定化する可能性があるので対処したいところです。
練習しないで、あきらめの心境になると?
前述のタイプとは逆に、「心が極端に、闘うことをあきらめてしまう」と、「準備を途中でやめる」「話す機会を避ける」「完全に意気消沈する」などの状態になりやすいです。
練習のやり過ぎによる硬さは生まれませんが、心が闘っていないので、心身がパフォーマンスを発揮しようとしません。
例えば、面接試験で不合格が続いた人などは、闘う気持ちが低下して、この「あきらめる、逃げる」メンタルポジションになっていることもあります。
そして、練習不足なので、あたふたと対応して、本番を終えてしまう。
結果として話す機会を「心地よいものとは思えない」ので、ますますストレスに感じる人もいます。

古垣講師
練習を完全にやめるのも、萎縮して余計に緊張してしまう面があるのです。
お勧めの取り組み方は、ほどほどの闘う気持ちを持つこと
時間を決めて練習するなど、メリハリをつけながら練習をすることがお勧めです。
「そうは言っても、不安で練習をやってしまう」という人は、緊張や不安のスイッチをOFFにするために、別のことに没頭する時間を持ちましょう。
例えば、運動をする、料理をするといった時間を持つと、本番を意識することを忘れられて、気持ちが落ち着くことを感じやすいです。
それでも不安な人は、当会では認知行動療法で、自分の心の奥を見つめることを実践して頂いています。
本番を意識するのは、「自分自身をどこか不器用だと捉えている」など、考え方のクセが潜んでいることがあるためです。

古垣講師
また、技術面にはある程度の自信を持つことも推奨です。
「話しやすい、情報の組み立て方」を知っていると、練習をし過ぎなくても本番で十分なパフォーマンスを発揮しやすくなります。
むしろ、何度も練習をしなくてはいけないのは、勝手が分からずに自己流で挑み続けて、その不安から緊張に陥っていることがあります。また、そのパターンに気が付かずに繰り返す人も少なくありません。
練習時間を「ほどほど」に収めつつ、情報を整えるコツで話しやすさを向上させておく。
そうした対処で、本番時の緊張感と話のパフォーマンスが変わっていきます。

「考えて話せない」「人前で緊張する」などの「話す悩み」に対する適切な学び方を、論理的に解説。「話し方の改善の道筋」が分かる一冊です。当会のメール配信(無料)に登録後、ダウンロードできます。

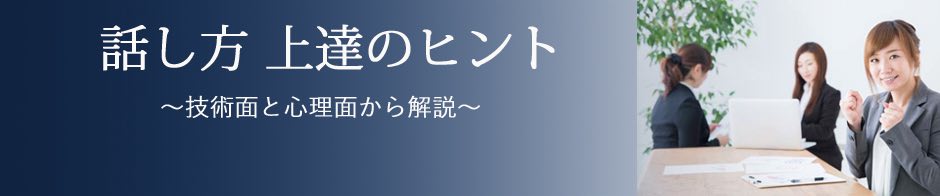

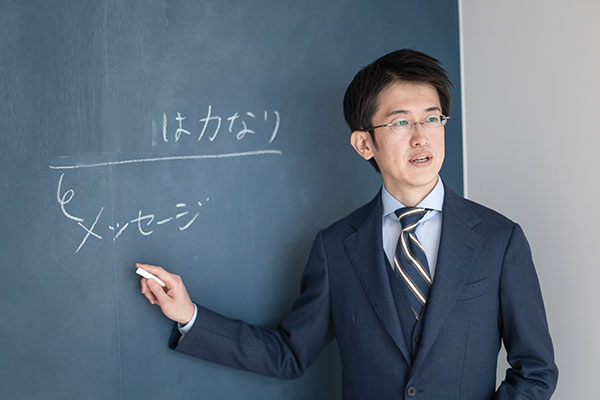



 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康