
古垣講師
スピーチに向けて「良いネタ」がないと探し続けることはありませんか?
スピーチで陥りやすいのが、情報収集に力を入れてしまうこと。
その中でも注意が必要なのが、「面白い体験」や「人を驚かせるネタ」を探すことです。
確かに、「面白い体験」「人を驚かせるネタ」を用意できれば、話の内容に自信をもてる面はあります。
しかし、こうした路線でスピーチづくりを続けると、朝礼など「定期的に話す場」では、次の機会に向けた準備がツラくなりやすいです。
自分の中で面白いネタの水準を維持しないといけない、そんな他人からの印象を維持しようとする心が生まれ、毎回のネタ選びが難航することがあるのです。

古垣講師
むしろ定期的に話すために必要なことは、情報収集よりも「情報編集」に舵を切ることです。
情報編集に舵を切るとは、「何気ない日常の話」を活かして、聞き甲斐のあるスピーチを作ることです。
その場合に話の中心となるのは、体験の珍しさではなく、日常から自分が何を得たか。
そうした、思索や気付きの面白さでスピーチを仕上げるのがコツになります。
| 例:日常から自分が何を得たか |
|---|
| 昨日、久しぶりに訪れたお店で、店員さんに丁寧に対応して頂き、あらためてお店のファンになった。そうした経験から「〇〇の姿勢が、ファンを作る」と学んだ。 |
| 以前に仕事で困ったときに、チームのサポートに救われた。「困っときには、〇〇が大事」だと知った。 |
誰にでも起こりそうな出来事でも、そこから「自分が何を得たか、学んだか」は、自分だけの感じ方や考え方が反映されます。
だから、固有の魅力があるので、聴衆にとって聞き甲斐のある話になりやすいです。

古垣講師
何気ない日常の話でも、他の人では語れない価値が話に加わります。
情報編集で気をつけたい点ー思索の語りの長さ
気をつけたいのは、思索の語りが長すぎる話は、理屈っぽく聞こえること。
なるべく体験談をしっかり描いて、考えたことを長々とは述べないこと。
もともと考えることが好きな人は、思索に触れた箇所が長くなりがちなので、注意が必要です。

古垣講師
どのように構成すると良いのか、次でご紹介します。
情報編集で気をつけたい点ー構成感
| 構成の例 |
|---|
| 序論:全体像を示唆 |
| 本論:体験談を展開 |
| 結論:体験を踏まえた思索を述べる |
大切なのは、雑談ではなく、思索に向かってきれいに情報が流れるスピーチに仕上げること。
そのためには「結論」を設定して、余計な箇所を、きれいに省いておくことも必要です。
こうした構成感次第で、聴衆の集中力は変わります。

古垣講師
とくに「何気ない日常」を題材にする場合は、構成感に配慮しないと変化に乏しい内容を長々と語る印象を与えます。
ぜひ、ネタを探す「情報収集」よりも、話をつくる「情報編集」の腕を磨いてみてください。
ちなみに、「情報編集力」を磨いておけば、突然のスピーチでも、話をスムーズに準備できます。
入門編「ラクに話せる文章の基礎」+「本番力が身につく練習法」」
放送業出身の講師が教える、「スピーチを覚えて話す」ための動画レッスン。
ひとりでも本番並みの負荷を味わいながら、スピーチ練習ができます。

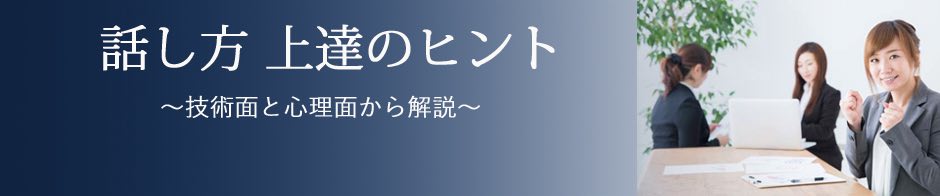

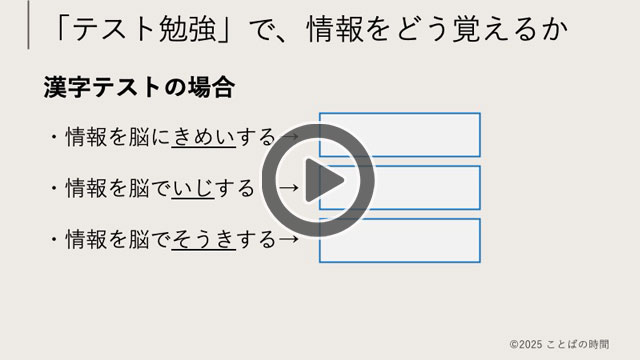

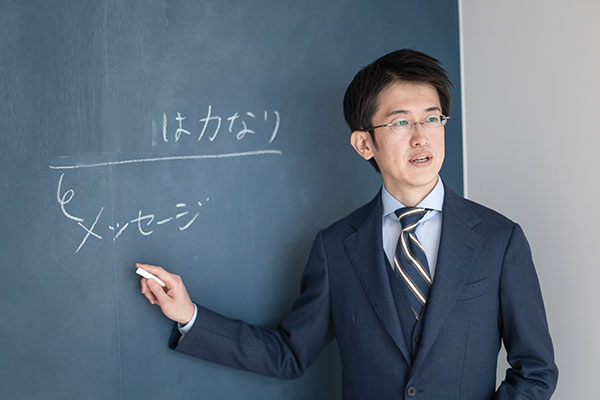


 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康