話の途中で内容をすっかり忘れてしまったことは、ありますか?
とくにスピーチやプレゼンの大事な場面で、穴が空いたようにぽっかりと、「何を話すべきだったか」を思い出せないことがあります。

古垣講師
一度経験すると、「また起きるのでは?」と不安になる皆様も多いです。
今回の記事では、話を「ど忘れ」したときの対処法や、準備の段階で必要なことを紹介しています。
ど忘れするのは、なぜ?
簡単に表現すると、頭の余力がないときに、話す内容をど忘れします。
緊張時には、認知資源と呼ばれる「頭の余力」が少なくなりがちです。
だから、平時ならスラスラと話せることも、緊張すると想起するための頭の余裕がなくて苦労しがちです。

古垣講師
とくに話が飛ぶのは、情報量の多い文章を話し終わった直後です。
頭の余力が少ないときに、情報量の多い文章を思い出すのは、脳の大きな負担になります。
ただ、練習しておけば、多くの方は「情報量の多い文章」までは、なんとか話せます。
ですが、その箇所を話し終わると、頭の余力(認知資源)が一時的に枯渇します。
そのため、その先を思い出す余力を失いやすいです。

古垣講師
だからこそ、情報量が多い箇所を事前に調整することが、「ど忘れ」の予防策としてもっとも大事なのです。
ただ、話が飛びやすい人ほど、情報の要不要の判断が、思い切りがよくないことがあります。
あれも必要、これも必要だと、色々と気遣いして情報を盛り込むため、情報量が増えてしまうことがあるのです。

古垣講師
本番で安定感のある話をするために、情報を盛り込んだ箇所を整理しておくことが肝心です。
しかし、それでも本番でど忘れしてしてしまったら、どうするか。次の項目で対処法をご紹介しています。
ど忘れしたときの対処法

色々な人のスピーチを見てきた経験上、もっとも記憶を戻せる確率が高いのは、沈黙するのではなく、「何かを語り続けながら、記憶が戻るのを待つ」ことです。
例えば、「話が飛んだ箇所」の言葉を繰り返し、関連する話をそれとなく続けてみるのも一手です。
| 話を続けて、記憶が戻る例 |
|---|
| 先日、ショッピングモールにいったんですが フードコートに話題の天ぷら屋が出店していて、驚きました。 (↓話したい内容を忘れたので、「話題の天ぷら屋」という言葉を繰り返す。また、それに関連する話をそれとなく続ける) ・・・そこには、今話題の天ぷら屋がオープンしていたんですね。 (ここで、テレビの影響力を語りたかったことを思い出す) |
このように、関連する話を続ける中で、「もともとはこれを言いたかった!」という情報を思い出せることがあります。
カウンセラーも、相談者の話が飛んでしまったときに、それまでどのような話をしていたかを振り返ってもらう中で、その先の内容を思い出してもらえることがあります。
あるいは、講演会などで時間をかけて複数の項目に触れるときは、忘れたらあまり粘らずに「思い出したら話しますね」といって、他の項目に移った方がよいこともあります。他のことを話す中で、自分が伝えたかったことを思い出せることもあるからです。

古垣講師
いずれの場合も、沈黙ではなく、語り続ける中で、言葉に紐づいて内容の記憶が戻ってくることが多いです。
ど忘れしないための、話の練習法

前述のように、原稿の情報量を調整することは、まず考えて頂きたいポイントです。
さらに、記憶するための練習法も、コツがあります。
ときどきお見かけするのが、原稿を眺めながら、覚えることに時間をかける皆様です。
実は、それ以上に必要なことは、思い出す練習をすることです。

古垣講師
認知心理学などの世界で知られていますが、記憶には、「記銘(覚える)→保持(キープ)→想起(思い出す)」という段階があります。
話をど忘れする場合、基本的には話を覚えているけれど、本番で「思い出せなくなる」人が多いです。
だから、想起(思い出す)の部分までを意識して、練習をしておく必要性があります。
なお、一言一句まですべて覚えるか、あるいは重要な単語を中心に覚えるのか。その辺りは、話す目的に応じて、ふさわさしい練習が必要です。
式典などのスピーチは、一言一句を間違えずに話すべき場もあります。
しかし、小規模の集まりにおけるスピーチは、そこまでの練習は不要なことが多いです。
ただし、いずれの場合でも、話の情報整理と話す練習が適切でないと、記憶が抜けやすいと感じます。
当会では、話す目的に応じたふさわしい練習法をご紹介しています。

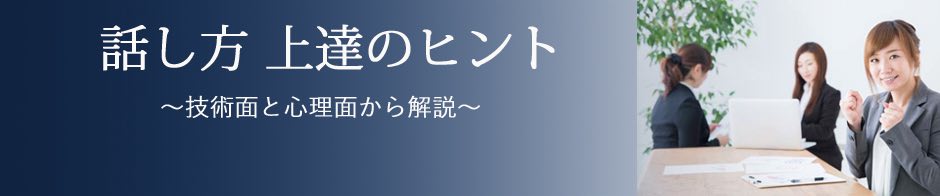


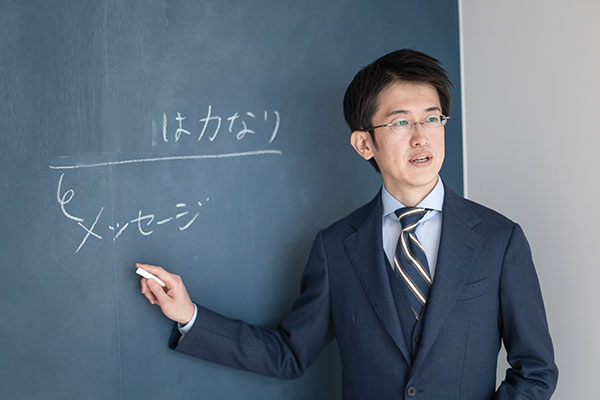



 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康