他人の話を聞くときに、以下のような感想を持つことはないでしょうか。
| 人の話を聞いて、客観的に思うこと |
|---|
| 「話が長い」と感じる(聞き飽きる) |
| 「頭が一杯になる話」だと感じてしまう |
| 複雑で分かりづらく、途中から聞く気が無くなる |

古垣講師
他人の話なら、こうした感想を持つことが可能なのですよね。
しかし、いざ自分が発表用の原稿を用意する際、「聞きやすい話を作ること」は、わりと大変です。
発表内容にこだわりを持って作るほどに、
- ・聞く人を最後まで疲れさせない
- ・話がシンプルで理解しやすい
こうした配慮をすることが、難しくなります。

古垣講師
「話を聞く人の努力で、最後まで付き合ってもらっている」という例も、実は多いです。
「最後までストレスなく聞ける話」を準備するためには、話を客観視するチカラが必要です。
そのチカラを伸ばす方法を、今回は2つ紹介します。
1. 話を録音して聞く
例えば、「自分の料理が美味しいかどうか」を知るには、調理の際に味見をしますよね。
話の場合は、「自分の話を録音して、聞いてみる」ことで、聞きやすい話かどうか、点検しやすくなります。
「原稿を眺めるだけ」だと、話を聞くときの負担をイメージしづらいことが多いのです。
というのも、情報を「聞く」ことが「読む」よりも、脳の負担が高いからです。
| 耳から情報を聞く |
|---|
| 言葉や文章を頭に一時保存しながら理解をする。頭から情報が抜けたら理解できないので、努力して言葉や文章を頭に留める必要性がある。 |
| 目で情報を読む |
|---|
| 原稿上に情報が書いてあるので、頭にすべての言葉や文章を留める必要がない。忘れたら、原稿を読み返せば良い。 |

古垣講師
こうした違いがあるため、情報を「耳で聞く」と、目で読むよりも頭が一杯になりやすいのです。
「耳から情報をインプットする」ことで、ようやく
・情報量が適切か
・理解しやすい内容か
といったことを聞く人の感覚で味わいやすくなります。
例えば話を聞いてみて、「なんとなく長いな」「この辺りでアタマが疲れる」といった感想を持てたら十分です。
それが、伝える内容を見直すための足場となります。
なお、録音した直後は「客観的な評価」が難しいので、避けましょう。

古垣講師
録音したら少し時間を置くと、「話し手の気持ち」から離れて客観的に聞きやすくなります。
2. 他人のやり方を参考にする
例えば、「他人の作った美味しい料理」を食べると、「自分の作る料理」を客観的に評価しやすくなります。
できれば、スピーチや講演も、他人の話をしっかり観賞すること。
今は、リアルでもネットでも、そうした機会を得やすい時代です。
上手な伝え方を聞くと、「分かりやすい」「最後まで話が頭に入る」そんな感覚を味わえます。
とくに、自分の発表と似た種類の話を、他人がどのように上手に伝えるか。
その実例に触れることで、「耳で聞いて分かりやすい話」を感覚的に把握することができます。
すると、自分の話を見る目が変わっていきます。
なお、話し方教室では、直接、講師からフィードバックを得られます。
すると、「自分の話を客観的に分析する視点」が詳細に分かり、話の点検に役立ちます。
人前での話し方講座~情報構築と記憶術~
(スピーチ原稿の作成力向上)
説明力を磨く 個別レッスン
(説明、プレゼン原稿の作成力向上)
経営者、専門家、管理職向けスピーチ個別レッスン
(経営者や管理職のスピーチ作成力向上)
スピーチ原稿 執筆サポート
(本番用原稿の作成を相談しながら進められる)

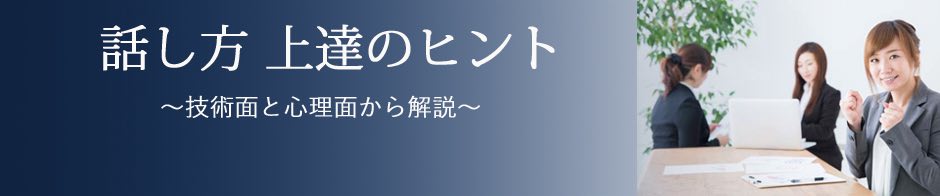

 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康


