| こんなお悩みはありますか? |
|---|
| 大勢の前に立つことが不安で、ストレスを味わいやすい。 |
| 失敗することが怖くて、練習を続けたくなる。 |
| 結果の見通しが立たないことについて、心配しがち。 |
誰しも緊張はしますが、「心配しやすい」ことから緊張が余計に高まるケースがあります。

古垣講師
「先回りして、心配事に対応したがる人」が陥りがちです。
その仕組と対策について、今回のコラムでご紹介しています。
闘争‐逃走反応を知る
そもそも、話すときに緊張してしまうのは、「闘争‐逃走反応(ウォルター・B・キャノン,1929)」と呼ばれる体の仕組みが関係しています。
人の体は危機を感じたときに、体が警戒態勢になり、交感神経系の働きを活発にして、闘ったり逃げたりする準備をします。
例えば話すときに「私の話はどのように評価されるだろう」などの不安から警戒態勢になり、交感神経系の働きが活発になります。
その働きが過剰になると、心拍数の上昇や体の震えといった影響が現れます。

古垣講師
この闘争-逃走反応を過剰にさせるのが、心配しすぎるタイプの人です。
心配しやすい人は「話が飛んでしまったらどうしよう」「失敗したら、どう思われるだろう」などわずかな不安でも、クローズアップして捉えてしまいます。
このタイプは、良く言えば検討力があって、さまざまなことに気がつく人かもしれません。
ただ問題となるのは、自分の危機感を高めてしまうことです。
心配は「ほどほど」にすればよいのですが、完璧主義的に心配し、危機感を抱いてしまう。
その原因はいくつかありますが、多い事例と対策を以降でご紹介します。
なぜ心配してしまうのか その原因と対策
反応的に考える
もともと直感的に行動しがちな人は、不安が浮かびやすいことがあります。
理性によるブレーキをかけながらじっくり吟味するのではなく、自分の感覚に基づいて行動しがちな場合です。
その場合の対策は、一呼吸おいて行動するメンタルワークや、理性的に自分の言動を検証する力を育てることが大事です。

古垣講師
直感だけに任せず、適度なブレーキを、自分に備えていくことが大切です。
「自分なら対応できる」という自信が乏しい
例えば、人前で話す際に「失敗したらどうしよう」「自分に対応できるだろうか」と不安になる。それは、自分が「自分なら大丈夫と思える感覚」が乏しいことから生まれやすいです。
ご相談の際に「自分に自信がない」という声をしばしばお聞きしますが、そうした人もこのタイプに含まれることが多いです。
その場合の対策は、もともと「どこか不器用である自分」を知ることが多く、その心理面を見つめながら、苦手な面の改善などを図っていくことが対策になっていきます。

古垣講師
場合によっては、「話の技術面の学び」で、自信を底上げすることが必要なこともあります。
社交場面が苦手
もともと、社交場面が苦手であったり、他者との関わりに自信を持てないから、不安を抱きやすいケースもあります。
その場合の対策は、コミュニケーションの基礎力から磨くことで、人との関わりに安心感を持てるようにすること。
また、そもそも人に対する不安があれば、その点を心理的なサポートで緩和していくことがお勧めです。

古垣講師
対人不安が強ければ、心のカウンセリングがお勧めです。
入門編「緊張とうまく付き合い、人前で積極的に話す」 動画講座
10年以上にわたり、支持されてきたプログラムの入門編。
緊張の高ぶりを鎮めながら、緊張時のストレスに強くなるワークに取り組めます。
緊張感を固定化する「先回り行動」を制御する
心配しやすい人は、先回りして考えることが習慣であることが多く、いろいろな対策をしがちな場合があります。
しかし、認知行動療法で「安全確保行動(安全行動)」と呼びますが、自分の失敗を回避しようと「過剰な行動」をする場合は、緊張感を固定化することがあります。
| 先回り行動(安全確保行動)の例 |
|---|
| 失敗が怖くて、延々と練習をする |
| 一言一句を原稿の通りに話さないと、不安になる |
| 心配からお酒を飲む、甘いものを食べる |
これらは認知行動療法の中では、緊張感を固定化させないために、習慣を変えるトレーニングをすることがあります。

古垣講師
先回り行動をしなくても、自分に安心感を与えられる習慣を考えていきます。
方法を得ながら、経験を積む
当会を受講する方は、もともと不安が強い人も少なくありません。
ただ、受講しながら自己分析をする機会がたくさんあります。そしてトレーニングをすると、自己評価が変わっていく面があります。
「もっと自分を信頼してもいいかな」と徐々に感じられるようになります。
以上のように、心配しすぎて緊張などに繋がっている場合は、技術面と心理面にわたって対策を検討することが、お勧めです。
追記;不安が大きく、生活に明らかに支障を来しているような場合は、一度、医療機関を受診することが勧められます。

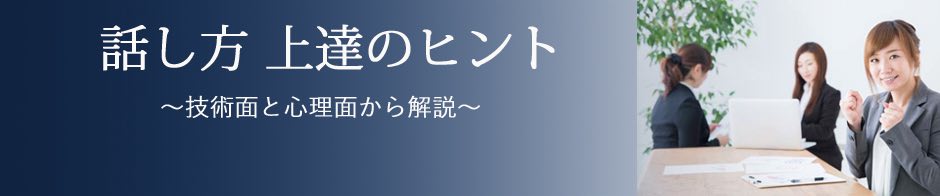




 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康