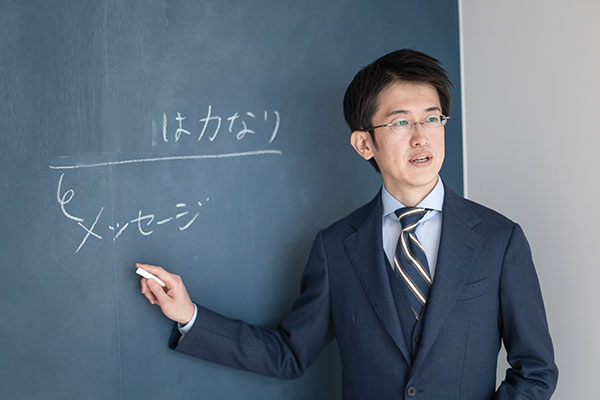| こうしたお悩みはありますか? |
|---|
| ・具体的な点を、長く話しすぎてしまう。 (説明や報告、プレゼンが長くなりがち) |
| ・簡略化すると、簡単に語りすぎてしまう。 (スピーチや報告が短く終わる) |
「何をどれほど話すのか」は、人前で話すために重要なポイント。

古垣講師
上手な人ほど、重要な要素を上手に抽出して、話をします。
この記事では情報を抽出する技術の基本をご紹介します。
抽象度の調整力を磨く
「抽象」という言葉がありますが、これには「特徴を抽出する」という意味があります。
また、特徴を抽出した度合いを、「抽象度」といいます。
抽象度は、抽象と具体の間で変化します。
抽象:シンプルに伝える
↑
この間で、情報の抽象度を変えられる
↓
具体:ディテールを伝える
抽象的になるほど、シンプルな伝え方になります。
一方で具体的になると、情報量が増えていきます。
これらの間の「ちょうどよい抽象度」で話ができない。
だからこそ、話がまとまりがなく、ダラダラと話し過ぎてしまう。
あるいは、シンプルにしようとして、短く終わリ過ぎる。
「要領良く話すことが難しい」という悩みには、以上のような「抽象度の調整」が関わることがあるのです。
| 例:具体的な情報の、抽象度を調整 |
|---|
| 元原稿「私はリーダーとしてチームメンバーの業務についてのスケジュール表を作り、進捗を確認しました」 |
| アレンジ原稿「私はリーダーとして、チーム内で業務の進行管理をしました」 (下線部が情報を抽象的にシンプル化した箇所) |

古垣講師
「口下手」というよりは、こうした情報の扱い方に慣れていないために、うまく伝えられないことが多いのです。
整理するから、抽象化できる
当会のレッスンでも、
「ここを削るとまとまるのですね!」(抽象化がわかる)
「こういう風に具体を語れるのですね」(具体化がわかる)
こんな風に意外性を感じながら、情報の抽象度の変え方を知る皆様が多いです。
ちなみに「意外性を感じる」のは、ご自身としては「具体寄り」「抽象寄り」のいずれかにするのが、習慣になっていた場合です。
| 伝え方が具体寄りになる人の習慣 |
|---|
| 「細やかに話したほうが伝わる」と考え、情報量を増やしがち。 |
| マニュアル作成を担当するなど、情報を網羅することがクセになっていた。 |
| 伝え方が抽象寄りになる人の習慣 |
|---|
| 考える際の負荷がニガテで、大雑把に伝えてしまいがち。 |
| 専門的な抽象度の高い世界に順応し、専門用語など使いがち。 |
| 過程よりも「結果」に着目し、多くのことを省略して語りがち。 |
こうした「自分なりの伝え方の習慣」によって、具体寄りや抽象寄りの偏りが生じることがあります。

古垣講師
多くの人が、「抽象度」で話を客観視すると、それまでの習慣に気づきやすくなります。
なお、重要なポイントが一つあります。
「結局、自分が何を伝えたいのか(話の軸)」を整理することです。
話の軸を整理しないと、話の構築を誤ることがあります。
例えば、抽象化する場合にも、何をポイントとして残すべきか。
具体化するにも、何を深堀りして語ると良いのか。
その焦点の合わせ方が、話の軸をよく考えて整理しないと、ブレてしまうことがあるのです。
これは、スピーチや説明、報告、プレゼン、講義や講演など、様々な場面で必要な技術だと言えます。
当会でも「情報の扱い方」を学ぶ中で、磨いて頂けるポイントです。
言語化の基礎力としてもオススメ
言語化が苦手な人は、「語彙が少ないから」と考える人が多いです。
実は、今回紹介したような「抽象化」が、わりと大事なのです。
自分が普段使う言葉の「抽象度」に着目すると、「抽象的でふんわりと伝えている」ことに気づくことがあります。
その場合、「もっと具体的な表現を使うようにしよう」と目指すことで、新たな言葉の表現を獲得することにも役立ちます。

古垣講師
私自身、メールを書くときなども、抽象度に注意しながら、表現を検討することが多いです。
ぜひ普段から、自分の発信の中で、抽象度を意識しながら言葉を選んでみてください。
「情報の伝わりやすさ」が、格段に変わります。

「考えて話せない」「人前で緊張する」などの「話す悩み」に対する適切な学び方を、論理的に解説。当会の推奨講座も掲載した一冊です。当会のメール配信(無料)に登録後、ダウンロードできます。

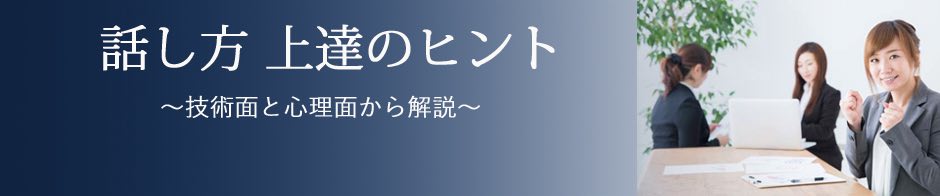

 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康