| こんな悩みはありますか? |
|---|
| 複数人で会話をすると、ついていけない。 |
| どこで会話の輪に入ったら良いかわからない。 |
| 3人以上、あるいは4人以上の会話に入れない。 |
当会でもご相談が多いのが、
「複数人のおしゃべりで苦手意識を感じて、なかなか積極的に話せない」
というお悩みです。

古垣講師
複数人のおしゃべりが難しい場合に多いのが、「会話のマルチタスク」が苦手という原因です。
複雑な情報の処理に頭が追いつかず、「本当はじっくりとしたペースで、一つ一つの話と向き合いたい」ことがあります。
対策として、とくに大切なポイントを紹介します。
対策1:「会話で何を求められているか」を見直す
じっくり考えるほどに、会話のマルチタスクがしづらくなります。
例えば、「アドバイス」や「切れ味するどい意見」を考えると、会話への反応が遅れます。
しかも相手の視点で考えると、アドバイスなどを求めたい訳ではありません。
むしろ相手の気持ちに共感したり、互いに言葉を交わすことをスキンシップとして楽しむ。
こうしたことが、「会話の目的」になることが多いのですね。

古垣講師
会話の努力が「相手の望まないこと」に向かっていないか、点検がお勧めです。
では、何をすればよいのか。
参考になることの一つが、漫才の「合いの手」です。
話を聞いたあとで、
- 「確かにそういうことあるな(共感)」
- 「えぇ、本当に!?(感情の表現)」
などと、相手の話を味わいながら、短い言葉を返す。
こうした対応をするためには、会話に含まれる情報だけでなく、感情にも関心を寄せること。
人間は個々に違う経験をしますが、その奥にある「驚きだった」「悲しかった」などの感情は互いに共感しやすいものです。
相手の感情に気づけるから、短い言葉でも気持ちのこもった返事になります。

古垣講師
瞬時に「相手の感情に気づく」ことが最初は難しくても、トレーニングをすると慣れていけます。
対策2:話したい欲求を持つ
会話で発言するのは、自分の中に「話したい」という欲求が生まれることがベースです。
その欲求があるからこそ、沈黙を破る突破力が生まれて、「自分も話そう」と思えます。
周囲にも話したい欲求は伝わり、自然と会話の順番がまわってくることもあります。
(「優先的に話したい」ような圧を発しているため)
このように、集団の中でも積極的に話すには、いくつかトレーニングした方が良い点があります。
その一つが、「話題に対して、強く発言したいと思える内容が浮かぶ」こと。
発言したいと思う気持ちは、「自分の体験」を会話と結びつけたときに生まれやすいです。
だから、人の話を聞きながら「自分の体験と結びつける」トレーニングがお勧めです。

古垣講師
ただし、「ダラダラと体験を語り過ぎて、話を占有しないこと」は、心がけたい点です。
対策3:より複雑な情報処理に対応しやすくなる
もともと社交場面が得意ではなく、3人以上、あるいは4人以上の会話に加わることが苦手な人がいます。
| 苦手になる理由 |
|---|
| 一度に行き交う情報量が増えて、自分の関わり方を見失う。 |
| いろいろな人が話すと、その処理だけで頭が一杯になる。 |
| 皆が話す話題に、付いていきづらい。 |
話に付いていくために、対策1のように「漫才の合いの手」のような対応ができることはお勧めです。
また、1人を相手にするときではなく、3〜4人と話すときに通じる話題は、少し性質が異なることがあります。
より、自分の関心がない話題が含まれる確率が上がります。
そんなときは、「話題について詳しく教えてもらう」ための、質問をする心得も必要です。
ただ、そもそも「情報を処理することが遅い」と感じる人は、情報構築の学びをしたほうが、効率よく聞いた情報を整理して、自分も話せるようになります。
当会でも、こうしたお悩みの改善の助けとなるトレーニングを行っています。

「考えて話せない」「人前で緊張する」などの「話す悩み」に対する適切な学び方を、論理的に解説。当会の推奨講座も掲載した一冊です。当会のメール配信(無料)に登録後、ダウンロードできます。

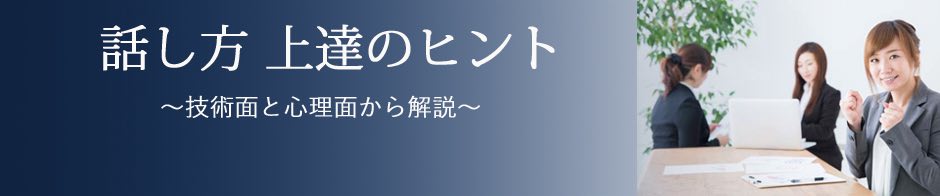





 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康