| こんなお悩みはありますか? |
|---|
| 急いで話すので、相手に聞き返されることがある |
| 自分では話す勢いを、調節しづらいと感じる |
| 気づいたら、一人で一方的に話そうとしている |
「焦って話をしてしまう」「つい早口になる」といったお悩みは、当会にもしばしば相談が寄せられています。

古垣講師
「改善を試みたけど、なかなか難しかった」という声も多いです。
なぜ、せっかちに慌てて話してしまうのか。その原因別に対策を紹介します。
原因1:「相手を観察して話す」習慣がとぼしい
伝えるためには、相手が話に付いてこれているか、様子を見ながら話をする必要があります。
しかし、せっかちに話す場合は、「相手の様子を観察する」よりも、自分が話すことだけに意識を向けてしまうケースがあります。
対策としては、話ばかりに集中せず、相手の様子を見る頻度を増やすこと。
その際に、相手が「話に付いてこれているか」を確認しましょう。
また、ときには「ここまでで、聞き漏らした箇所はありますか?」など質問をして、話が伝わっているか確認をしてもよいでしょう。
ちなみに、相手が理解しやすいよう、ときどき間をおくことも推奨です。

古垣講師
実は、少しの間があるだけで、多少は早口でも「話の聞き取りやすさ」は向上します。
原因2:頭の中の情報量が多い(隠れ情報過多タイプ)
例えば、情報の要不要の選別が、他人よりも割り切りがよくない。
あるいは、細やかに気を配って情報を網羅しがち。
以上の理由で伝える情報量が案外増えてしまい、しかも「全部を話さないと伝わらない」と感じる。
だから、早口で一気に話をしてしまう。(=慌てて話す雰囲気になる)
この場合の対策としては、情報をより精査する練習がおすすめです。

古垣講師
たくさん伝えても、相手はすべてを受け取れません。「これだけは伝える」という割り切りが肝心です。
情報を精査する練習については、以下のブログ記事も参考にしてください。
原因3:緊張感で一杯一杯になりやすい
早口を防ぐには、注意深く意識しながら、話すスピードを調整する必要があります。
しかし、緊張感で脳の余力が減ると、注意を話のスピード調整に向けづらくなります。

古垣講師
心理学に「認知資源」という言葉があるのですが、人の注意力には限りがあり、パフォーマンスの乱れにも通じがちです。
この場合は、緊張感を緩和して、脳の余力を少しでも取り戻すことが有効なケースがあります。
ただし、情報量が多いことが、脳の余力を減らしている可能性もあるので、ここまでご紹介した視点で総合的に対策を行うのが良いケースもあります。

「考えて話せない」「人前で緊張する」などの「話す悩み」に対する適切な学び方を、論理的に解説。当会の推奨講座も掲載した一冊です。当会のメール配信(無料)に登録後、ダウンロードできます。

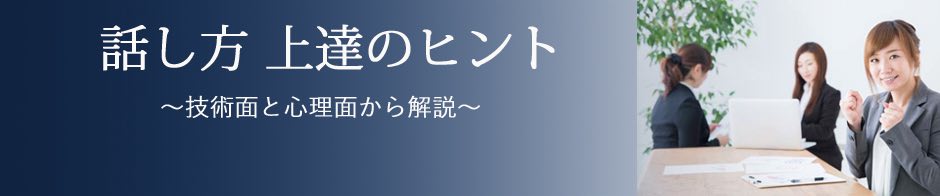

 【執筆者】古垣博康
【執筆者】古垣博康


